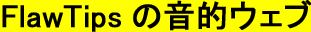Topページ > 共鳴
次は 声
|
音叉と共鳴箱
音叉というものがありますが、それを共鳴箱に取り付けると、音が鳴り出したりしますよね。音叉そのものが出す音は、非常に小さいものですが、共鳴箱が、その音を増幅しますよね。共鳴箱が、空気中からフリー・エネルギーを得ているかのようにも思えたり…(笑)。前にも書きましたが、音は空気を振動させたもので、それが耳の鼓膜を揺らす事によって「音」として聞こえるんですよね。「音」ってのは人間的な感覚かもしれないですね…^^;)
|
音叉
(一本〜セットまで色々あります)
下は120Hz程から上は2000Hz程まで様々な基準の音を出す音叉があります。440Hz付近は細かくて、442Hz,443Hzといったものもあります。持ち手の部分に工夫がしてあったり、共鳴箱付きだったり、脳外科用というのもあるようですね。そういうので、値段が異なったりします。音色の違いもあるそうです。
共鳴箱

楽器のチューニングでは、440Hz(ラの音)の音叉を主に使ったりしますが、音叉ヒーリングというのがあって「身体が共鳴する音」で少し書きましたが、体に音波を聞かせて調子を整えるものがあるそうですね。そういうのでは、色んな周波数の音叉が使われるそうですよ。
| |
ところで、小さく鳴っている音叉に共鳴箱を付けると、音が大きくなる理由は、エネルギーの再利用というか、合成というか、足し算というか^^;、そういうことが起こるからなんでしょうね。共鳴箱は、音叉の振動を受け取り、箱を振動させ、周りの空気を揺らすんですよね。共鳴箱は、音叉より振動する表面積が大きいので、空気を揺らす面積が広がって、音が大きくなったりするんでしょうね。
そして、更に、箱の内側で発生する空気振動が、壁の内側で反射を繰り返し、波の合成の原理で振幅が次第に大きくなるんでしょうね。振幅の大きくなった空気振動が、共鳴箱から外へ出て、耳に到達し、音が大きくなったように聞こえるんでしょうね。
音叉の場合は、その細長い棒が周りの空気を振動させてはいるんですが、反射の繰り返される場所が、棒の間だけに限られるので、殆どの振動が、空気中へ放射状に発散してしまって、振幅が大きくなるような増幅が起こらないのでしょうね。
余談ですが、増幅の原理は、何となく、太陽の集光による熱の発生ってことにも似てたりしますね(^^;?)。太陽光も「波」だから、音みたく合成したり、消したり出来るのかな?(謎)。まあ、単純にはいかないと思いますが。でも、放送局の電波が、建物などに反射して、受信状態が悪くなったりしますよね^^;
話を戻して^^;箱の両壁の距離が、ちょうど波長の倍数になっていると、波形が変わることなく合成され、振幅が一番大きくなるのかな?。ギターやバイオリンなど、共鳴するボディーを持つ楽器は、この原理で音を大きくしているんでしょうね。ボディーの材質の固有振動数や、形、ボディー内の木の出っ張りの大きさで音が変わってくるそうですよね。ボディー内の空気の振る舞い(合成や打消し)が倍音の構成を微妙に、変えるんでしょうね。弦の材質で、最初の振動の波形が変わるってのもあるんでしょうね。ボディーに適した弦の材質ってのもあるのかもですね。
Copyright (C) FlawTips All Rights Reserved.
|
|
|